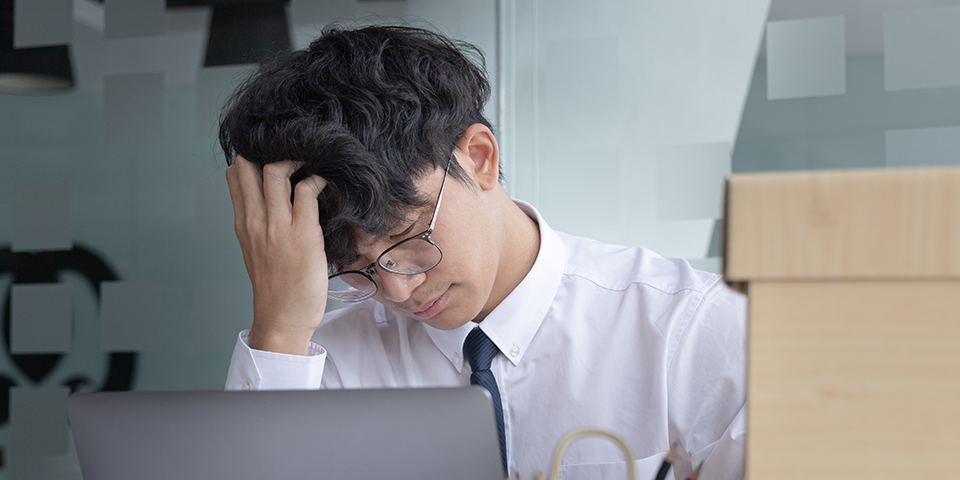Column
BtoBにおけるクリエイティブやデザインへの投資が及ぼす効果とは
〜リードジェネレーションへの投資だけで十分ですか?〜
- プランニング
- クリエイティブ
2025.04.23
2025.04.23
こんな人におすすめ
- 戦略立ててマーケティング施策を実施しているが、効果が上がらない
- マーケティングコンテンツの調達でデザインに悩まされている

BtoBマーケティングにおいて、広告やウェビナー、展示会やカンファレンス、そしてホワイトペーパーなどのリードジェネレーション施策は確かに重要です。しかし、それらの施策の効果を最大限に引き出すためには、単調に実施を繰り返すだけでは十分とは言えません。BtoBでは軽視されがちですが、実はその"伝え方"――つまり、クリエイティブやデザインへの投資が、リードジェネレーションのROIを大きく左右する要素となっています。
このコラムでは、BtoB領域におけるクリエイティブ/デザイン投資の波及効果について、多角的な視点から整理し、なぜ今あらためてこの分野への投資が重要なのかを考えていきます。
リードジェネレーション施策の限界と陥りやすい“消耗戦”
デジタル広告やホワイトペーパー、セミナー開催、展示会への出展など、リードジェネレーションの手法は多岐にわたり、そのプロセスは年々高度化しています。しかし、マーケティングの現場では多くの課題が聞こえてきます。
「クリック単価が上がりすぎて効率が悪くなってきた」
「資料請求はされるが、その後の反応が鈍い」
「広告表現が似通ってしまい、差別化できない」
こうした課題に共通しているのは、マーケティング活動が“手法”としてのリードジェネレーションに偏重してしまい、“伝え方の質”に対する投資が疎かになってしまっているということです。つまり、どれだけ優れたチャネル戦略を描いても、それを受け取る側――見込み顧客の「記憶に残る体験」になっていなければ、高い効果は見込めないのです。
広告もLPも、ホワイトペーパーも営業資料も、すべては"伝えるためのインターフェース"であり、そのインターフェースの質を担保するのが、まさにクリエイティブとデザインということになります。
デザインとは、単なる装飾ではなく戦略的な投資対象である
BtoBでは、「合理性」や「スペック重視」といった印象が強いため、デザインや表現に対する投資が後回しになりがちです。しかし実際には、デザインのクオリティがユーザーの体験を大きく左右し、商談化・受注の確率に波及的な影響を及ぼします。実際に、デザインやクリエイティブへの投資で高い効果を得られた事例は数多く、その一部を紹介すると、
- サービスサイトの構成を改善し、LPのビジュアルとコピーをリライト → CVRが1.8倍に向上
- ホワイトペーパーに図解とナラティブを取り入れ、DL後の商談率が2倍に
- 展示会用パネルや資料をリデザインしたことで、通りすがりの立ち寄り数が3倍に増加
こうした事例は、読み手の「理解しやすさ」「覚えやすさ」「話したくなる体験」を設計した結果です。そしてそれこそが、クリエイティブ/デザイン投資の真価と言えるでしょう。
デザインとは、美しく装飾することではなく、「伝えるべき情報を、伝えるべき相手に、正しく、心地よく届ける構造設計」でなくてはいけません。
クリエイティブ/デザインの波及効果
「広告・LPのCVR向上」
最もわかりやすい波及効果のひとつは、広告のクリック率(CTR)や、LP(ランディングページ)のコンバージョン率(CVR)の改善です。同じ広告文面・同じ訴求軸であっても、「フォントの選び方」「キービジュアルの印象」「ファーストビューの構成」「CTAボタンの配置や文言」などを整えるだけで、大きく結果が変わることは、マーケティング担当者であれば誰もが経験していることでしょう。
さらに、広告バナーで印象的なビジュアルやメッセージに触れた人が、後日ブランド名で検索して再訪する、いわゆる間接流入(アシスト効果)もデザインの影響と言えます。つまり、「その場でCVしなかった人の記憶にも残る設計」ができるかどうかが、その後の獲得効率を左右するのです。
クリエイティブ/デザインの波及効果
「商談化率の向上と社内共有のしやすさ」
ホワイトペーパーや事例紹介資料のような、いわゆる"教育系コンテンツ"においても、クリエイティブは極めて重要な役割を果たします。
たとえば、ただのテキスト資料よりも、「導入背景を漫画で描く」「数値の成果をインフォグラフィックで示す」「決裁者向けの“導入メリットサマリー”を1枚図にする」などの工夫があるだけで、読み手の記憶定着率や社内共有率が大きく変わります。
実際、"自社に導入すべき理由"を社内で説明する必要がある担当者にとって、「説明しやすい資料」であることは極めて重要です。デザインは、その「伝播のしやすさ」そのものを設計する力を持っているのです。
クリエイティブ/デザインの波及効果
「蓄積されていく“認識”と長期的な差別化」
クリエイティブ/デザイン投資のもう一つの効果は、長期的な“認識”の形成です。
顧客が合理的に比較・検討を行うと言われるBtoB領域においても、「なんとなくこの会社は信頼できそう」や「なんか印象に残っている」といった感覚は、最終的な選定の判断基準になります。人間が介在して行われる判断は、こうした感覚的な領域からは逃れることは出来ません。これはスペックの比較ではなく、“印象での比較”と言えます。
この“認識”を作るのが、ブランドガイドラインに基づいた一貫性あるトーンやデザインであり、Webサイトやバナー、資料、SNS、動画、展示会パネルに至るまで、あらゆる顧客接点において色使いや余白、文字サイズ、構成に共通性を持たせることで、無意識下に「ああ、◯△社の製品か…」という認識を形成していきます。
もちろん、その企業の持つ従来のイメージがポジティブなものである必要は言うまでもありませんが、こうした認識の刷り込みにまで到達した企業は、製品やサービスのスペックといった定量的な判断材料だけでなく定性的なアドバンテージを得ることになるので、マーケティングコストの構造が中長期的に改善していくはずです。
社内活用という“隠れた波及効果”
クリエイティブ/デザインの整備は、実は社内のコミュニケーション活性化にも大きく寄与します。
たとえば、
- 営業提案書のテンプレートが整っていることで、誰でも一定品質の資料が作れる
- MA施策のメールテンプレートがブランドトーンで統一されている
- 社内向けの説明資料やイベントパネルに至るまで、デザインの整合性がある
といった状態は、制作工程を削減して業務の効率化を高めるだけでなく、組織全体のブランド理解と一体感を高めます。これは属人化を防ぎ、提案活動や外部対応の品質を安定させる効果にもつながります。
ROIを高める「地盤」としてのクリエイティブ/デザイン
広告に投資すれば、リードは獲得できるかもしれません。ウェビナーを開けば、参加者も集まるでしょう。しかし、それだけでは競合と差をつけるには不十分です。受け皿となるコンテンツやクリエイティブの質が低ければ、せっかくの流入も機会損失に終わってしまうからです。
逆に言えば、あらゆるマーケティング施策とともに「表現力のあるバナー」「記憶に残るLP」「読みたくなる資料」「納得感ある提案書」が整っていることで、すべての施策のROIは大きく向上します。つまり、『クリエイティブ/デザインは単体でKPIを上げる施策ではなく、他のすべての施策の“土台を底上げする投資”』つまりはROIを高める地盤なのです。
伝わらなければ、価値は生まれない
いくら良いプロダクトを持っていても、どれだけ戦略的なリードジェネレーション施策を走らせても、それが伝わらなければマーケティング施策の効果は高まりません。そして"伝える"という行為の根幹を担うのが、まさにクリエイティブとデザインです。
特にBtoBマーケティングにおいては、表層的な“見た目”だけでなく、「理解を促進する構造」「選びやすくする情報設計」「社内共有を促す図解」「記憶に残る演出」といった、実務的な価値が必要ですが、こうした実務的価値を高めるためのメソッドが詰まっているのがクリエイティブ/デザインの領域です。
これからのマーケティングでは、「伝え方そのものに投資する」という発想が、あらゆる施策の成果を底上げする鍵となります。目先の“獲得のための投資”ではなく、“成果を増幅する投資”として、クリエイティブ/デザインへの取り組みを再定義してみてはいかがでしょうか。